遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、
株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前の連絡で土日祝も対応 |
|---|
自筆証書遺言の要件・メリット・デメリット・注意点等をわかりやすく解説します(自分で書く遺言書)
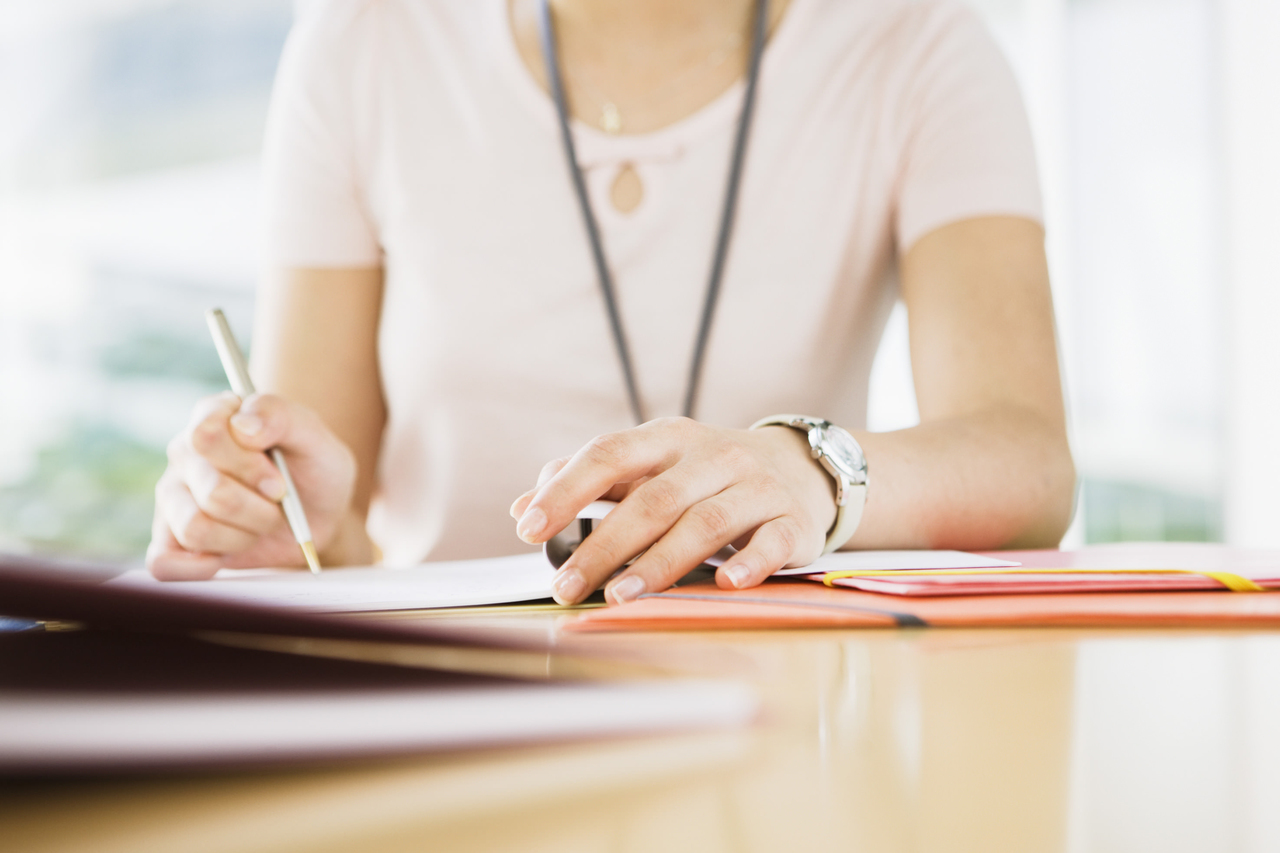
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文(文書のすべて)、日付、氏名を自ら書いて、これに押印したものです(民法968条1項)。
簡単に言うと、全部を自分で書いた遺言書です。
15歳以上であれば、誰でも遺言書を作ることができます。(民法961条)
ただし、法律上も正式に認められる遺言書といえるためには、民法で定められている方式に従って遺言書を作らなければなりません。(民法960条)
自分で、自己流に勝手に遺言書を作成した場合、たまたま民法で定められている方式に合致していれば、法律上の遺言書と認められますが、
民法で定められている方式に合致していなければ、法律上の遺言書ではないので、遺言した方の意思が書かれている文書ではありますが、何ら法律上の効果や拘束力を持ちません。
せっかく書かれた文書の内容や遺言をした方の意思が実現しない可能性が高くなります。
●「自筆証書遺言」は、簡単に自分で作ることのできる遺言書ですが、ちゃんと民法という法律で決められたルールに沿って作られていないと、法律上の遺言書ではなく、「遺言した人の意思が書いてあるただの文書」に過ぎないことになります。
そうなると、法律上の効力が認められない=遺言者の意思が実現されない ことになります。

メリット
①費用が抑えられる。
②自分一人で簡単に作成できる。
③内容を秘密にすることができる。
デメリット
①要件が厳格なので、民法で定められている方式に従っておらず、遺言書としては無効となる虞がある。
②遺言者の亡くなった後に、遺言書が発見されず、発見されても一部の相続人(遺言書の内容が実現すると不利になる相続人やその親族)によって内容を改ざんされたり、遺言書自体を隠されたりする虞がある。
③遺言書が法律的知識に詳しくない方によって書かれた場合、内容自体が不明確な内容(「あげる」「まかせる」といった曖昧な言葉を使用)だったり、抽象的な内容のため、遺言書の解釈に疑問点があり、後日相続人間の争いが起こる可能性があったり、遺言者の意図した内容が実現しないおそれがある。
④家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをする必要がある。
⑤視覚に障害のある方や、手が不自由な方にとって利用しづらい
(自書できない場合は利用できない)
●デメリットの多くは、遺言書に通じた法律の専門家によるチェックを受けないまま、一人だけで作成することによって生じることが多いので、
当事務所のような遺言書に通じた法律の専門家によるアドバイスのもとで、自筆証書遺言を作成されることをおススメいたします。
せっかく、大切な財産の処分方法について書いたもの、のこされる相続人の方が争わないために書かれたものなのですから、法律上も認められるきちんとした遺言書であるように、費用をかけてでも、法律の専門家の適切なアドバイスのもとで自筆証書遺言を作られることをおススメいたします。
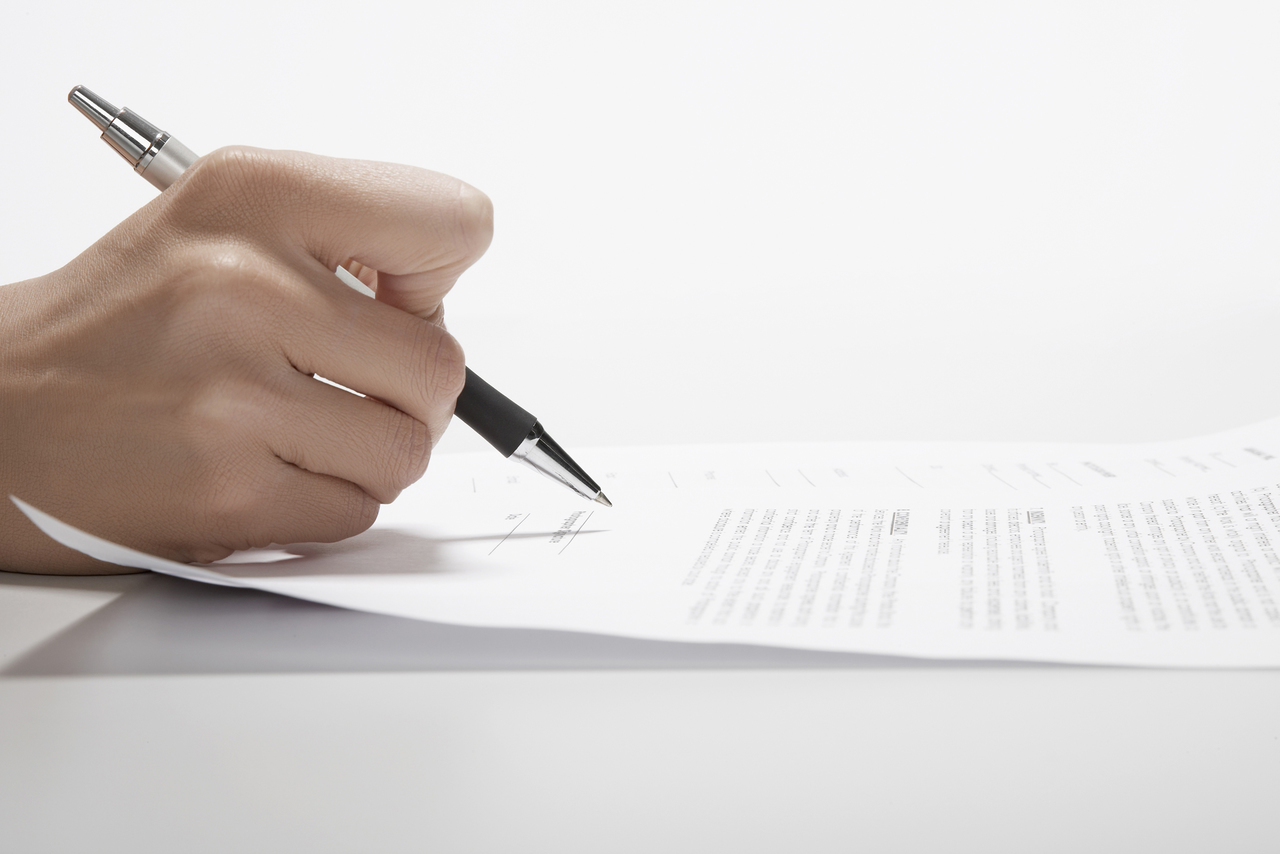
自書(自分で書くこと)が求められているのは、筆跡によって本人が書いたものと分かるので、それによって遺言した方の真意に基づいて作成されたことが分かるからです。
視覚に障害があったり、手が不自由である等の理由があっても、他人による代筆は認められません。
また、パソコンやワープロ等の機械を用いて作成することも認められません。
ビデオやテープ等の映像や音声の録音による方法もできません。
自書ができない場合には、秘密証書遺言もしくは公正証書遺言といった他の方法をとらざるをえません。
●「他人による添え手」について
病気その他の理由によって、自筆するにあたって他人の添え手による補助を受けながら作成された自筆証書遺言書については、
①自筆証書遺言書を作成時に自筆能力があること
②他人の添え手が、単に始筆や改行、字の間配りや行間を整えるために、遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまること、遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、添え手をした他人から単に筆記を容易にするため支えを借りただけであること
③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが、筆跡のうえで判定できること
以上の要件をみたす場合には自書として有効とされています。
(最判昭和62年10月8日を参照)
証人や立会人の立会を必要とせず、自分だけで簡単に作成できる遺言であることから、その他の遺言方法に比べて偽造・変造の危険性が最も高く、遺言者の本当の意思に基づいて作成されたものかどうか後日争いが生じやすい遺言方法であるので、「自書」の要件は厳しいものとなっています。
※ 高齢の方等にとって全文の自書(全部を自分で書くこと)はかなりの労力でした。
そこで、2019年の1月13日より、文書のうちで自書しなくてもよい部分が認められました。
遺言書に相続財産の目録を記載する場合については、相続財産目録については自書しなくても良い扱いとなりました。
相続財産目録については自書しなくても、ワープロやパソコンで作成したもので構わなくなりました。
不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを目録とすることも可能です。
ただし、目録の各ページに署名と押印が必要ですので、ご注意ください。

自筆証書遺言を作成していて、書き損じることもあるかと思います。
その場合の訂正も、民法で定められている方式に従って訂正しないと、訂正とは認められないので注意です。
訂正するには、
①遺言者自らが
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記した際には、署名すること
④訂正した箇所に押印すること
が必要です。
よほどでない限りは、書き損じた場合には最初から作り直すことをおススメいたします。
遺言者の財産を処分する方法等を書いたせっかくの文書、相続人の方にのこす大事な文書ですから、ミスのない綺麗な遺言書であったほうが良いと思います。
財産関係もきちんと把握したうえで、抽象的な記載やどのようにも解釈できるような記載をせず、入念な下書きをしたうえで、自筆証書遺言を自書されると良いと思います。
一度に書くことが難しければ、少しずつでも書かれたら良いと思います。
5.法務局で自筆証書遺言書を保管してくれます
2020年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度がスタートいたしました。
この制度のメリットは、
●面倒で時間のかかる検認の手続きが不要になること、
●遺言書を法務局で保管してもらえること
です。
検認の手続きが不要なので、遺言書に従って、スピーディーに遺言書の内容を実現することが可能になります。
また、遺言書を法務局で保管してもらえるので、「遺言者の死後に、遺言書が発見されず、発見されても一部の相続人によって内容を改ざんされたり、遺言書自体を隠されたりする虞がある。」というデメリットを解消できます。

遺言者は法務局に自筆証書遺言(無封のもの)の保管を申請することができます。
●どこの法務局でもというわけではなく、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)でのみ実施されます。
●遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地 を管轄する遺言書保管所で可能です。
●遺言者自らが法務局に赴いて、保管の申請を行う必要がある(代理人による申請はダメ)
●遺言書の閲覧、撤回は遺言者が自ら法務局に赴いて行う必要がある。
●遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧(遺言書の内容を確認)等を行うことはできない。
●この制度によって保管されている自筆証書遺言書については、検認が不要です。
ただし、気を付けたいことは、
この制度でも、自筆証書遺言書の内容まではチェックしてくれないことです。
遺言書の内容が、法律的に有効か無効か、実際に実現可能なものかどうか 等といった判断はしてくれません。
「遺言書が法律的な知識に詳しくない方によって書かれた場合、内容自体が不明確な内容だったり、抽象的な内容のため、遺言書の解釈に疑問点があり、相続人間で争いが起こる可能性があったり、遺言者の意図した内容が実現しない虞がある。」というデメリット
については、そのままなので、やはり自筆証書遺言書を作成される場合には、自分一人だけでは作成されず、遺言書に通じた法律の専門家によるアドバイスのもとで、自筆証書遺言を作成されることをおススメいたします。
当事務所では、既に作成された自筆証書遺言のチェックも行っております。
6.当事務所へご依頼された場合
当事務所は遺言書の作成や相続登記等の相続・遺言関係について得意としておりますので、
お気軽にご相談いただけたらと思います。
初回の相談は無料でしております。
遺留分にも配慮し、法律上有効な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の作成にあたり、不動産登記簿謄本等の取得が必要な場合には、当事務所で取得することも可能です。
遺言執行者への就任をお引き受けすることも可能です。
「のこされる方への思いやり、優しさ」として遺言書を作っておいてほしいと思います。
当事務所はその思いを全力でサポートいたします。

手続の流れ
当事務所へ自筆証書遺言の作成をご依頼された場合、
①ご依頼された方のご意向を十分に伺ったうえで、自筆証書遺言の文案を作成いたします。
②文案の内容をご確認いただきます。
③文案にご納得いただいたうえで、文案を自書していただきます。
④清書された自筆証書遺言をチェックいたします。
作成済みの自筆証書遺言のチェック
すでにご自身で作成済みの自筆証書遺言が法律上も有効なものか、記載内容に漏れや不備はないかといったチェックを行なうことも承っております。
●すでにご自身で作成済みの自筆証書遺言のチェックの費用
(法律的に有効か、記載漏れはないか等)
1万6500円~ (※税込)
※事案の難易度等によって異なります。
費用
●当事務所で自筆証書遺言の文書内容の起案を含めてご依頼される場合
3万3000円~ +実費 (※税込)
※事案の難易度等によって異なります。
●実費
戸籍謄本の収集や不動産登記簿謄本、不動産の評価証明書の取得等が必要だった場合、
その費用
郵送費
※実際にご面談をしたうえで、財産の内容、相続人との関係、ご意向等を伺ったうえで、
費用に関しては御見積をさせていただきます。
電話・メール等での御見積は対応いたしかねますので、ご了承願います。
当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話または下記のフォームにて受け付けております。
出張等で不在時は携帯に転送されます。
営業時間中に留守番電話になった場合は、
お名前とご用件をお伝えください。
折り返しご連絡いたします。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
Menu
インフォメーション
お問合せ・ご相談
お問合せはお電話で受け付けています。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
ご面談(出張を含む)による無料相談を行っております。
お電話・zoom等直接お会いしない形式の相談は行っておりません。
受付時間/定休日
受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
(事前連絡で土日祝も対応)
アクセス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
<電車をご利用の方へ>
JR京都線 新大阪駅より徒歩5分
阪急京都線 南方駅より徒歩5分
地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
<お車をご利用の方へ>
事務所近くに有料パーキングがございますのでご利用ください。