遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、
株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前の連絡で土日祝も対応 |
|---|
相続法改正の押さえておきたい重要ポイント
(変更点)をわかりやすく解説します
今回なされた相続法改正の押さえておきたい重要ポイント・変更点は、大まかに下記の8点あります。

ご夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者の方は、それまで住み慣れた建物に引き続き居住することを望むことが多いものです。
特に高齢化社会が進む中、残された配偶者の方も高齢者であるという場合が増えてきており、住み慣れた建物を離れて新たな生活環境に移ったり、引越し等なされることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となることが考えられます。
高齢のうえ、収入も年金だけであるということも多いので、新居を探そうにも貸してくれないといったことも考えられます。
そこで、高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権(住み慣れた建物に住み続ける権利)の保護の必要性が高まっていたため、この制度が設けられました。
① 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、相続開始後(被相続人の死亡後)、遺産分割協議が成立するまでの短期間、相続開始以前と同じように使用し住み続けることのできる権利です。(民法第1037条)
最低でも相続開始後6カ月間は居住し続ける(住み続ける)ことができます。
●相続開始時から遺産分割協議が成立するまでの短期的な居住権を保護するもの
●相続開始時に被相続人名義の建物に無償で居住(タダで済んでいる)していること が要件
●配偶者に内縁の配偶者は含まれない
●使用できるだけ。収益権はなし(家を貸す など収益をあげることはできない)。
相続開始以前の使用が建物の一部分だけの使用だった場合は、全部ではなく一部だけの使用が可能。
●遺産分割協議により居住していた建物の帰属(所有者)が決まるまで、もしくは相続開始後6カ月経過するまで、のいずれか遅い日まで居住できる
② 配偶者居住権
配偶者短期居住権が、「相続開始時から遺産分割協議が成立するまで」の短期的な居住権を保護するものであるのに対して、
配偶者居住権は「遺産分割協議の成立後から亡くなるまで終身」の長期的な居住権の保護を目的としています。
所有権よりも安い価格で居住権を確保することができるようにすることで、相続財産のうちの預貯金等の金銭を取得しやすくする狙いがあります。
居住権は所有権と異なり、建物を所有しないが住み続けることのできる権利、建物を使用できる権利なので、所有権より金額が安くなります。
住み慣れた住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金としての預貯金等の金銭を一定程度確保できるようにすることが目的です。
●亡くなられた方の配偶者が、
相続開始時に被相続人名義の建物に居住している場合で、
ⅰ)遺産分割協議 または ⅱ)遺贈
により配偶者居住権を取得することが要件です。
遺贈に限定されているのは、配偶者居住権を取得したくない場合、相続だと、それ以外の部分も含めて全てを放棄(相続放棄)せざるを得ませんが、遺贈だと配偶者居住権の部分だけ放棄が可能だからです。
●期間について特別に定めない限り、配偶者の終身が期間となります。
●登記が第三者対抗要件です。
(居住建物の所有者は配偶者に配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います)
第三者対抗要件とは、私が居住権を持っていますよと、他人に主張し認めてもらうためには、登記しなければなりませんという意味です。
●配偶者短期居住権と異なり、以前の使用が建物の一部だけであったとしても、建物全部を使用できますし、収益権もありますので、家を貸すこと(賃料収入を得ること)も可能です。

①持ち戻し免除の推定
以前の民法では、遺産分割の場面において共同相続人の中に、被相続人からの遺贈や生前に贈与を受けた者がいる場合には、共同相続人間の公平を図るために、その特別な贈与を相続財産に持ち戻して、個々の相続人の具体的な相続分を計算する扱いとなっていました。
(簡単に言うと、一部の相続人だけ特別に得をさせません という扱い。
生前の贈与の分を、相続時点の財産である相続財産に戻して(持ち戻し)計算するということ。
相続発生時点の財産+生前の贈与財産 を基準に相続分を計算する)
但し、被相続人が明示もしくは黙示に特別な贈与を持ち戻す必要がない旨を意思表示していた場合には、持ち戻し計算する必要はありませんでした。
但し、そのような持ち戻し免除の意思表示がなされることは実際少なかったので、適用される場面が限られていました。
そこで、
①婚姻期間20年以上の夫婦の一方配偶者から、他方配偶者への遺贈又は贈与
②上記遺贈又は贈与の対象が居住用建物又はその敷地であったこと
上記要件を満たす場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定して、遺産分割の場面において特別な贈与の持ち戻し計算を不要としました。
持ち戻し免除が推定されることで、遺贈・贈与を受けた配偶者は遺産分割の場面で、他の相続人に比べて、多くの相続財産を取得することが可能になりました。
②仮払いの制度
平成28年12月19日の最高裁判決において、預貯金債権は遺産分割の対象となりました。(この裁判例以前は、金融機関に対する預貯金等の金銭債権は、相続分に応じて当然に分割される扱いでした=自分の法定相続分については払戻請求可能)
この最高裁の裁判以降、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議を経なければ金融機関に対する預貯金債権を引き出すことはできなくなりました。
相続人の全員の同意による遺産分割協議が成立するまで預貯金を引き出せない不都合(遺言書がなければ、遺産分割がまとまるまでの長期間お金を引き出せない)を解決するため
以下の、仮払いの制度が設けられました。
①一定額の預貯金の払い戻し制度
②家庭裁判所の保全処分による引き出しの要件緩和
①につき、各共同相続人が裁判所の裁判を経ることなく、各金融機関の窓口において、遺産に含まれる預貯金の払戻を受けることができるようになりました。
預貯金残高×法定相続分×1/3
但し、上限は各金融機関ごとに150万円とされています。
②につき、遺産分割の審判、調停を申し立てる場合に、亡くなられた方の借金や入院費等の債務の弁済や残された相続人の生活費のため、「預貯金債権を行使する必要性がある場合」(従前は「急迫の危険を防止するために必要がある場合」と要件が厳格でした)には、家庭裁判所の判断によって、預貯金債権の一部を申し立てた者に仮に取得させる処分ができることになりました。
要件が緩和され、預貯金の一部払い戻しを受けることができる場面が広がりました。
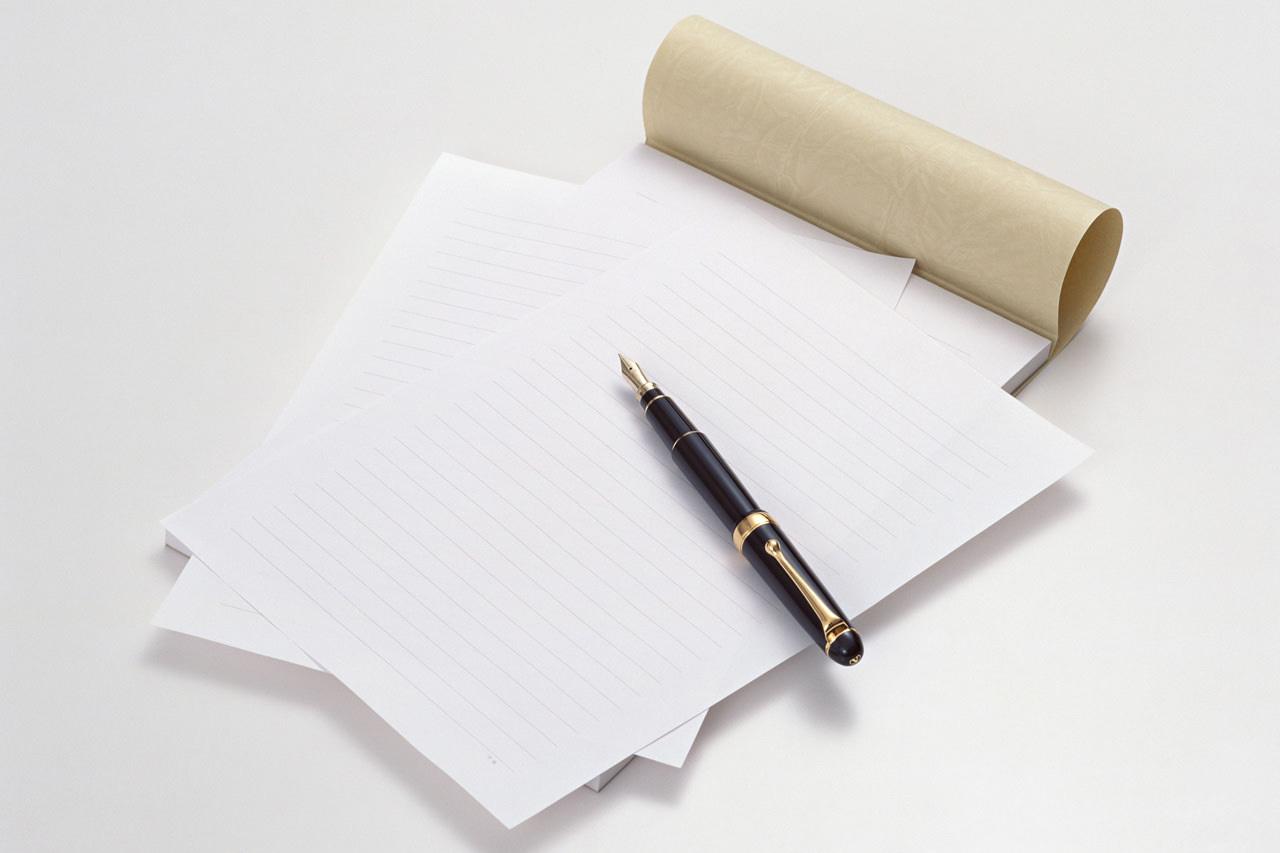
自筆証書遺言の方式(要件)が緩和されました。
自筆証書遺言では、全文、日付、氏名 を自書し、
押印する必要があります。
しかし、高齢者にとって全文の自書はかなりの労力でした。
そこで、遺言書に相続財産の目録を記載する場合は、相続財産目録を自書しなくて良いこととなりました。
相続財産目録については自書しなくても、ワープロやパソコンソフトで作成したものを印刷したもので構いません。
不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを目録とすることも可能です。
ただし、目録の各ページに署名と押印が必要です。

①自筆証書遺言書の保管制度の創設
遺言者は法務局に自筆証書遺言書(無封のもの)の保管を申請することができます。
●どこの法務局でもというわけではなく、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)でのみ実施されます。
●遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地 を管轄する遺言書保管所で可能です。
●遺言者自らが法務局に保管の申請を行う必要があります(代理人による申請はダメ)
●遺言書の閲覧、撤回は遺言者が自ら法務局に赴いて行う必要があります。
●遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
●この制度によって保管されている自筆証書遺言書については、検認が不要です。
②遺言書保管事実証明の交付
遺言者の死亡後、何人も遺言書保管の有無、保管されている場合には作成年月日、保管されている保管所の名称等を記載した書面の交付を求めることができます。
●どこの遺言書保管所に対しても可能
●遺言者の死亡後、自分が相続人や受遺者になっている場合には、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧請求が可能、遺言書情報証明書の交付請求も可能
●相続人や受遺者が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を求めた場合、遺言書保管所は遺言書を保管している旨を相続人や受遺者、遺言執行者に通知を行います
◎自筆証書遺言保管制度のポイント、注意点など を別のページにて、詳しくよりわかりやすく解説していますので、自筆証書遺言にご関心ある方は是非下記をクリックしてご覧ください。

①遺言執行者は相続人に対して、相続財産目録の交付だけでなく、遺言書の内容を通知しなければならなくなりました。
②遺言書に遺言執行者の権限が明確に定められている場合はそれが優先されます。
一方、遺言書に遺言執行者の権限が特別に定められていない場合で、特定遺贈がなされ遺言執行者がある場合には、当該遺贈行為を遺言執行者のみが行うことができるとされました。
さらに、遺言者が「次男にA土地を相続させる」等といった遺言(特定財産承継遺言)をした場合に、遺言執行者がある場合には、遺言執行者はその相続人が対抗要件を備えるために必要な権限が認められました。
※登記申請の権限があるのは、2019年7月1日以降にされた遺言によって、遺言執行者に選ばれた場合だけです。
対象の財産が預貯金の場合には、遺言執行者に払戻請求、解約の申し入れをする権限が認められました。(但し、解約の申し入れは対象となる財産が預貯金の全部である時に限ります)
③遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができるとされました。
遺言執行者が法律的知識のない相続人である場合、やむを得ない事情がなくても、法律専門職に遺言執行の委任をすることが容易にできることになりました。

遺留分減殺請求権とは、被相続人の死後のこされた相続人の生活の保護や相続への期待を守るために、法定相続分の半分に関しては、要求することができる権利です。
兄妹姉妹以外の相続人に認められています。
権利なので、権利を行使しないことも可能。
これまでは、遺留分減殺請求権を行使すると、 現に遺留分の対象となった財産を持っている人と共有状態になるとされていました。
その結果、紛争当事者間で対象物を共有することになるため、共有関係の解消を巡って、さらなる新たな紛争が生じる事もよく見られました。
そこで、遺留分減殺請求者は、侵害者に対して侵害された遺留分の金額に相当する金銭の支払いを請求することができると改めて、 遺留分減殺請求を金銭的な解決が可能なものとしました。

相続によって法定相続分を超える権利を取得した場合には、法定相続分を超える部分については、一律不動産登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとされました。
以前は、取得の方法により、対抗要件を具備する必要性に違いがありました。
例えば、
①遺産分割による権利の取得の場合には法定相続分を超える部分については登記が対抗要件である。
②遺言書による遺贈による権利の取得の場合には、登記しないと権利の取得自体を第三者に対抗できない。
③遺言書による相続分の指定の場合には、法定相続分を超える部分を含めて登記しなくても第三者に対抗できる。
④「次男にA土地を相続させる」等といった遺言書に基づく場合には、法定相続分を超える部分を含めて登記しなくても第三者に対抗できる。
しかし、相続関係や遺言書の中身の分からない第三者にとっては、遺言書の記載内容次第で、権利の取得が左右されるので、不測の損害を被る可能性を否定できませんでした。
そこで、相続による権利の取得については、遺言や遺産分割によるものかどうかを問わず、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないこととしました。

例えば、被相続人の看護を相続人である長男の妻が行っていたような場合、改正以前は、長男の妻は相続人ではないことから、相続財産を相続によって取得できず、直接的にその貢献に報いることはできませんでした。
今回の改正により、被相続人の親族が無償で、被相続人の財産の維持・増加に一定の貢献をした場合について、その親族を「特別寄与者」として、一定の要件のもと、「特別寄与料」を請求できることにしました。
●親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をさし、内縁の配偶者は含みません。
●親族間の相互扶助義務を超えた、多くの親族が通常行うと期待される程度を超える貢献であることが必要です。
●施設に入所させて、毎日見舞い程度では認められません。
●無報酬やそれに近い状態で療養看護がなされる必要があります
●仕事の傍ら、通って介護していた程度では難しく、専属的に療養介護を行う必要があります。
●貢献によって、実際の看護費用の出費が免れたことも必要です。
当事務所では相続法改正にも精通しており、最新の法令に従って、依頼者の方にとってベストなご提案・ご対応をいたします。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話または下記のフォームにて受け付けております。
出張等で不在時は携帯に転送されます。
営業時間中に留守番電話になった場合は、
お名前とご用件をお伝えください。
折り返しご連絡いたします。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
Menu
インフォメーション
お問合せ・ご相談
お問合せはお電話で受け付けています。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
ご面談(出張を含む)による無料相談を行っております。
お電話・zoom等直接お会いしない形式の相談は行っておりません。
受付時間/定休日
受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
(事前連絡で土日祝も対応)
アクセス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
<電車をご利用の方へ>
JR京都線 新大阪駅より徒歩5分
阪急京都線 南方駅より徒歩5分
地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
<お車をご利用の方へ>
事務所近くに有料パーキングがございますのでご利用ください。