遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、
株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前の連絡で土日祝も対応 |
|---|
相続財産管理人とは?相続人がいない・いるかどうか不明な場合の対処方法、手続等を丁寧に解説します。
(相続財産管理人を選任しないための対策についても解説)

1.相続財産管理人の制度とは
亡くなられた方(被相続人)に相続人がいるのか、いないのかよく分からない場合や相続人がいないことが分かっている場合(相続人全員が相続放棄をして、その結果誰も相続人がいなくなった場合も含まれます。)
には、家庭裁判所に対して申立てをすれば、相続財産管理人を選任してもらえます。
相続財産管理人は、相続人を捜索しながら、相続財産の散逸を防止すべく管理や亡くなられた方(被相続人)の債権者等に対して被相続人の借金や費用の支払等の清算事務を行い、
清算後に残った財産を国庫に引き継がせます。
被相続人と特別の縁故のあった方(特別縁故者)に対して相続財産を分け与える場合もあります。
●簡単にいうと、相続財産管理人は相続人の捜索や相続財産の管理・清算を行う者です。

2.相続財産管理人の選任が必要な場合
亡くなられた方(被相続人)に相続人がいない場合に放っておくと、誰も相続財産を管理しませんし、債権者への支払いも行いません。
相続人のいない相続財産は最終的には国庫に帰属しますが、放っておいて勝手に相続財産が国庫に帰属することもありません。
そこで、誰かに相続財産を適切に管理させて、必要な支払いや国庫に帰属させる仕事行わせる必要があります。
その仕事を行う者が相続財産管理人です。
亡くなられた方に相続人がいるのか、いないのかよく分からない場合や、相続人がいないことが分かっている場合に、必ず相続財産管理人選任の申し立てをしなければならないわけではありません。
亡くなられた方に目ぼしい財産が何もなければ、相続財産管理人を選任する意味がないからです。
実際には、亡くなられた方に相続財産管理人を選任する意味があるだけの相応な相続財産があって、かつ相続財産管理人を選任してもらいたい方がいる場合に申し立てが行われます。
①被相続人の債権者が債権の回収を行いたい場合
②被相続人の特別縁故者が相続財産の分与を受けようとする場合
③亡くなられた方と不動産を共有する方が共有持分を取得しようとする場合
などが考えられます。
亡くなられた方にお金を貸していた債権者には、お金を返してもらう権利がありますが、相続人がいなければ、どうやってお金を返してもらえばよいのかわかりません。
また、亡くなられた方が誰かに対して特定の財産を遺贈する旨の遺言書を書いていた場合、遺贈を受ける人(受遺者)はどうやってその財産をもらえばよいのかわかりません。
相続人がいなければ、相続財産の清算事務を行う者がいないため、上記のような場合に困ってしまいます。
そこで、亡くなられた方に相続財産管理人を選任する意味があるだけの相応な相続財産があって、相続財産の清算を希望する方がいる場合には相続財産管理人選任の申立てが必要となるのです。
亡くなられた方に相続人がいなくても、相続財産がほとんどなかったり、相続財産があっても上記のような相続財産の清算を希望する者がいない場合には、誰も相続財産管理人の選任申立てを行わないので、相続財産管理人が選任されることはありません。
相続財産管理人の選任申立てを行うことは義務ではありません。

3.特別縁故者とは
特別縁故者とは、亡くなった人と生計を同じくしていた人(内縁の妻、事実上の養子や養親など)や、亡くなった人の療養看護に努めた人などです。
亡くなられた方の親族や生前に交友関係にあった等、通常の交際の範囲を超えない縁故は特別縁故者にあたりません。
亡くなられた方の葬式、納骨等の祭祀法事を行っただけでは、特別縁故者にあたりません。
葬式費用は、当然には亡くなられた方に対する立替金債権にあたりません。
(葬式は喪主が主催する儀式であり、費用は喪主が負担することが原則との考えのためです)
特別縁故者と認められることは簡単なことではありません。
裁判所によって特別縁故者と認められれば、相続人でなくても亡くなった方の財産を与えてもらうことが可能となります。
特別縁故者として相続財産の分与を請求する場合には、その前提として相続財産管理人の選任申立てが必要となります。

4.相続財産管理人の権限
相続財産管理人は、相続財産に対する「保存行為」や「管理行為」は自らの判断でできます。
保存行為とは相続財産の現状を維持する行為、
管理行為とは物や権利の性質を変えない範囲で利用・改良する行為になります。
具体的には、
・不動産の相続登記
・預貯金の払い戻しや解約
・借金や費用等の債務の弁済
・賃貸借契約の解除
等を自らの判断でできます。
ただし、家庭裁判所の許可を受ければ、相続財産に対して「処分行為」も行うことができます。
具体的には、
・不動産の売却
・家電や家具の処分
・亡くなった人の位牌の永代供養
・蔵書の寄贈
・定期預金の満期前解約
などの処分行為を行いたい場合には、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、許可を受ければ行うことが可能となります。
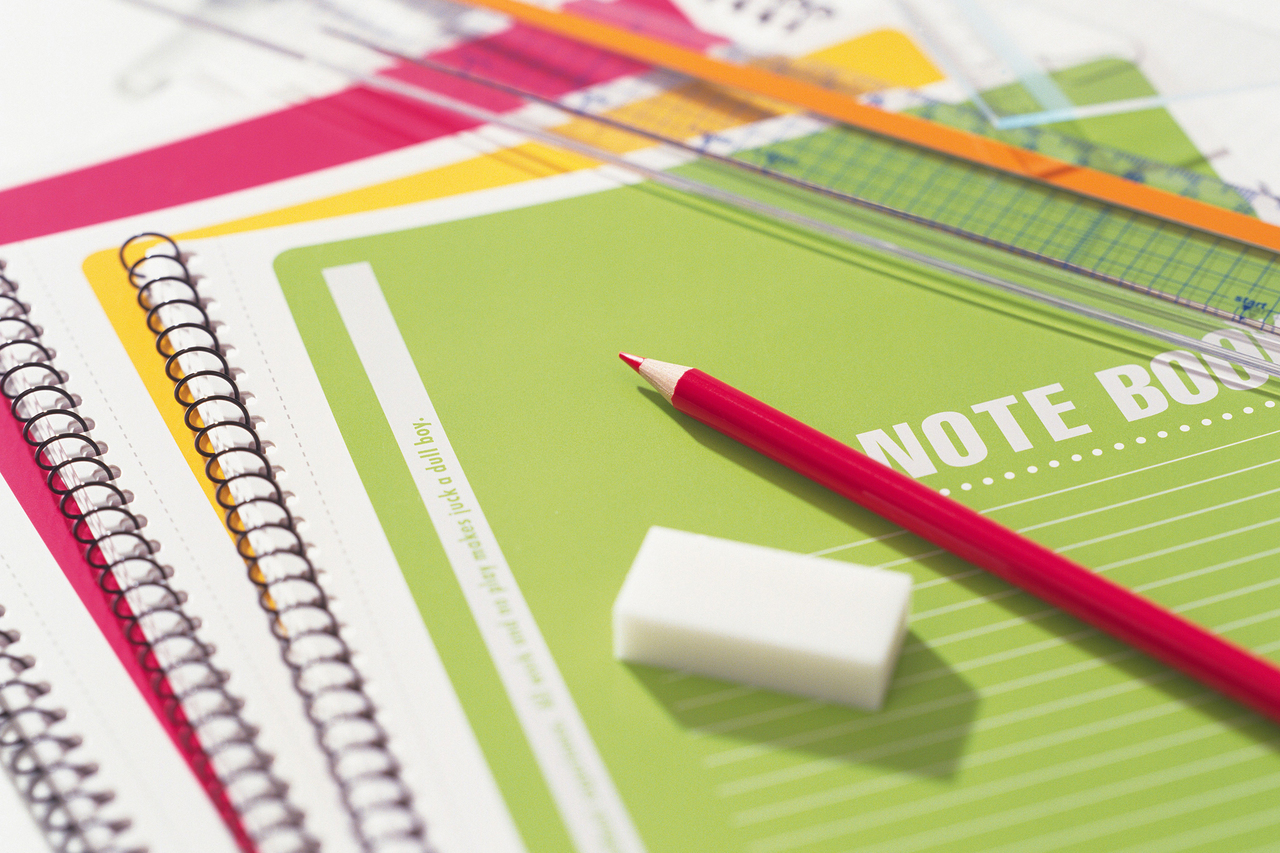
④申立てに必要な書類
①相続財産管理人選任審判申立書
②亡くなられた方(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③亡くなられた方(被相続人)の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④亡くなられた方(被相続人)の子供(及びその代襲相続人)で死亡している方がおられる場合、その子供(及びその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤亡くなられた方(被相続人)の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹で死亡している方がおられる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦代襲相続人としての甥姪(亡くなられた方の兄弟姉妹の子供)で死亡している方がおられる場合、その甥又は姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑧亡くなられた方(被相続人)の住民票除票又は戸籍附票
⑨財産を証明する資料
(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
⑩利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証明する資料
(遺言書、戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書の写し、特別の縁故の事実を疎明する資料等)
⑪相続財産管理人の候補者がある場合には、その方の住民票又は戸籍附票
⑫相続関係図
⑬相続人が相続放棄を行った場合は、相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄等有無の回答書(発行後3か月以内のもの)
⑭上記①~⑬のすべての写し(副本)
※戸籍等はすべて謄本(全部事項証明書)でなければならず、抄本(一部事項証明書)ではありません。
※提出した戸籍等は原則として返してもらえません。

7.相続財産管理人を選任後の手続
以下の手続の途中で相続財産が無くなった場合は、そこで手続は終了します。
①家庭裁判所は相続財産管理人選任の審判をしたときは、相続財産管理人が選任されたことを知らせるために公告を行います。
②上記公告①から2か月経過後に、相続財産管理人は相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行います。
③上記公告②から3か月経過後に、家庭裁判所は相続財産管理人の申立てによって相続人を捜すために6か月以上の期間を定めて公告を行います。
公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人が不存在であることが確定します。
④上記公告の期間満了後3か月以内に特別縁故者は相続財産分与の申立てを行うことができます。
⑤相続財産管理人は必要に応じて随時、家庭裁判所の許可を得たうえで、相続財産である不動産や株式の売却等金銭の換価行為を行います。
⑥相続財産管理人は、債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって、特別縁故者に相続財産を分与するための手続を行います。
⑦債権者等に対する支払等をしてもなお相続財産が残った場合には、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
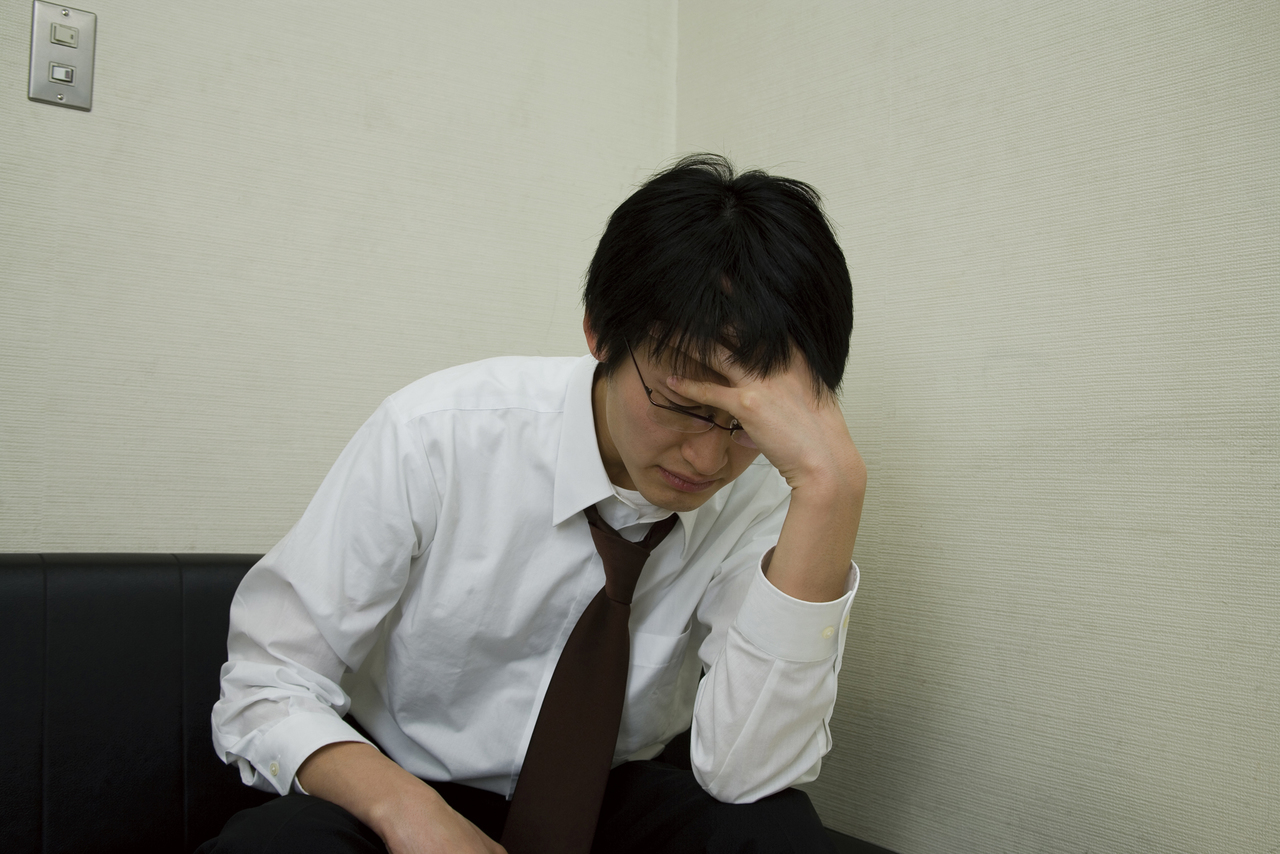
8.相続財産管理人の制度利用の現状
相続財産管理人選任申立ての際には、相続財産管理人の報酬などに充てる費用として、おおよそ100万円程度の予納金を納めなければならないのが実務上の取り扱いです。
申立人が支払った予納金は、相続財産の清算を行ったうえで、余らなければ返してもらえません。
また、自らを特別縁故者と考える方が財産の分与の請求をしても、必ず認められるというわけではありません。
仮に分与が認められたとしても、実際に相続財産を受け取るまでには多くの手間と時間がかかります。
多額の予納金や多くの手間と時間がかかることから、相続財産管理人や特別縁故者の制度はあまり利用されていないのが現状です。
亡くなられた方の財産がそのまま事実上放置されているケースも、決して珍しいことではありません。

9.相続財産管理人を選任しないための対策方法
自分が亡くなっても相続人がいないという場合には、
①判断能力がしっかりしているうちに遺言書を作成して、自らの財産の処分方法について指定しておくことが非常に有効です。
遺言書に遺言執行者(遺言者の死後に遺言書の内容を実行する者)について記載をしておけば、遺言執行者が相続人や相続財産管理人に代わり相続財産の処分を行うことができるからです。
また、遺言書で遺言執行者を指定していない場合でも、遺言書の内容によっては内容の実現のために、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立てをすることができる場合があります。
②相続人がいないけれどお世話になった方や親族がいる場合には、養子縁組をしておくことも有効です。
たとえば、世話になっているが相続人にはあたらない親族などがいる場合に、遺言書も作成せずそのまま死亡すれば、その親族は利害関係人として相続財産管理人の選任申立てを行い、相続財産管理人を選んでもらうことがまず必要です。
その後、様々な公告期間を経過した後に、特別縁故者への財産分与の申立てを行い、その申立てが無事に家庭裁判所に認められた場合に限って、相続財産をもらうことができます。
しかも、そのときにもらえる金額は家庭裁判所が決定する金額となります。
このようなことを避けるためには、相続財産をあげたい人と養子縁組をしておくのも有効な方法です。
養子と養親は互いに相続権を持つので、養子縁組をしておくと、その後に亡くなっても、その人が遺産を相続することができます。
●まとめますと、将来相続財産管理人を選任しないためには、
①遺言書の作成を行う
②養子縁組を行う
以上の2つの方法が有効です。
そして、いずれの方法も、自分の判断能力がしっかりしているうちに行うことが大切です。
いざ、認知症等で判断能力が低下してから行っては、十分な判断もできません。
お子様がおられないなど相続人がおられない方は、しっかりとしている今のうちから対策を取ってほしいと思います。
司法書士おおざわ事務所は、あなたのお力となり全力でサポートさせていただきます。
将来の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。

11.当事務所にご依頼された場合の費用
●費用
5万円(税抜き)~+実費
(事案の難しさなどにより変動します)
※司法書士は、家庭裁判所での手続について代理人となれませんので、申立書の作成や提出書類の収集とそれらの提出を行います。
●実費
提出する戸籍謄本等の費用や郵送費など
遺言書の作成等 相続に関するご相談は司法書士おおざわ事務所の得意とするところです。
また、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行う際に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)等はかなり多くの通数が必要ですし、素人の方だと戸籍を読むこともままなりません。
専門家ではない一般の方が自分で戸籍等を取得し、亡くなられた方の相続関係を調査するのは大変な労力と時間がかかり大変です。
そこで、相続財産管理人の選任を申し立てを行う場合には、司法書士等の法律専門家に依頼されることが多いのが実情です。
司法書士おおざわ事務所では家庭裁判所に提出する申立書の作成のみならず、戸籍等も取得いたしますので、面倒な相続人不存在の調査をすべて行います。
相続財産管理人選任の申立てをご検討の際は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、遺産分割協議書の作成や遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話または下記のフォームにて受け付けております。
出張等で不在時は携帯に転送されます。
営業時間中に留守番電話になった場合は、
お名前とご用件をお伝えください。
折り返しご連絡いたします。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
Menu
インフォメーション
お問合せ・ご相談
お問合せはお電話で受け付けています。
事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。
ご面談(出張を含む)による無料相談を行っております。
お電話・zoom等直接お会いしない形式の相談は行っておりません。
受付時間/定休日
受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
(事前連絡で土日祝も対応)
アクセス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
新大阪サンアールビル北館408号
<電車をご利用の方へ>
JR京都線 新大阪駅より徒歩5分
阪急京都線 南方駅より徒歩5分
地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
<お車をご利用の方へ>
事務所近くに有料パーキングがございますのでご利用ください。



